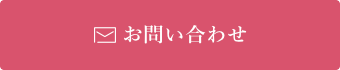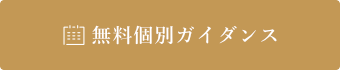9月入学者向けオリエンテーション 【アウトプットと抽象度】

先日9月からスタートされた生徒さんたちへ、
受講の心構えや学び方、マインドセット、理論の大枠を伝えるセッションを行いました。
全員が揃うことは出来ませんでしたが、
こうやって顔合わせして仲間の存在を感じることで緊張が解けたり、
練習会に出席しやすくなったりするといいなと思っています。
30分程度の予定が
大幅に伸びてしまいました。
ついつい、教えたくなってしまう。
相手がきちんと受け取れているか、確認しながらいかないといけませんね。
私たちは、自分がもう初心者ではない分野については、
つい専門用語を使ったり
つい専門用語を使ったり
説明をはしょったりしがちですよね。
相手が自分と同じように知っているかのように、
いろんな背景や前提を省略して話したりしてしまいます。
最初は「わからん」と悩みながら知識を得ていったにもかかわらず
最初の頃のことは忘れてしまうんです。
抽象度とアウトプット
この講座では必須の「抽象度」
抽象度はあげたり、下げたりできることが大切。
上げるだけではダメなんですね。
学者さんが専門分野のお話を、いつも通りに説明しても、
小学生たちにはちんぷんかんぷん、何も入らないでしょう。
頭のおかしな人が変なことを言っている、と思うかもしれません。
抽象度が高い(その専門分野についてたくさんの知識を包摂している)だけではダメ。
必要な時には抽象度を下げて、
分かりやすく(できれば面白く!)話せるのがいいんですよね。

なので、うわべだけの知識を詰め込んだだけでは、抽象度が高いとはいえず。
上っ面だけじゃないならば、子供にもわかりやすく出来るはずなんですよね。
自分が学ぶだけなら、理解できていればいいですよね。
インプットしただけでよくて
例えば「AはBだからCである」と覚えたらそのままでいい。
でも、アウトプットするためには、それだけではダメですよね。
アウトプットしようとすると、
なんで? Bって何? 次の定義のDとは何が違うんだろうか、と
説明が必要なことがどんどん出てきてしまいますよね。
なので。
アウトプットは大事です☺更に、他人に教えるためには
どの角度からも説明できないといけないし、
たいていは初心者の方に教えると思うので
抽象度を下げたり、上げたり、出来ることが大切ですよね。

感想を書くだけでも、
自分がどう思ったかを書くだけでも、
その講義や本やワークのどの部分を切り取るか・・
どの部分への感想なのか・・
振り返ってまとめることが必要になったりします。
ということで、
グループセッションが終わった後は、簡単にシェアを書いてもらうようにしています。
将来、お客様に「認知科学って何?」とか
「どうして書き換えられるの?」とか
聞かれたりするであろう生徒さん達が慣れる場を作るようにしています。
ちょっと偉そうですがーー
私もシェアや感想が苦手で。
学ぶことばかりでアウトプットしてこなかった反省も込めて。
今日も最後までありがとうございました。
LOVE
関連エントリー
-
 「美容気功」と女性である私の本音
世間の美容気功とTransformation式美容気功は同じか 先日書いたこのブログ 「癒され方が、違う」お読
「美容気功」と女性である私の本音
世間の美容気功とTransformation式美容気功は同じか 先日書いたこのブログ 「癒され方が、違う」お読
-
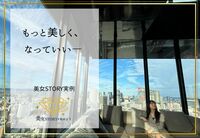 美への道は、ほんの小さな勇気から
人生が変わるほどの美容を美容気功家の華世です。 先日の体験会で、こんなことがありました。 彼女は、体験会に来る
美への道は、ほんの小さな勇気から
人生が変わるほどの美容を美容気功家の華世です。 先日の体験会で、こんなことがありました。 彼女は、体験会に来る
-
 右往左往しない、美容
今朝、YouTubeを流し見していたら、 とある動画がふと目に入りました。メイクやコスメ、ドクターまで含めて、
右往左往しない、美容
今朝、YouTubeを流し見していたら、 とある動画がふと目に入りました。メイクやコスメ、ドクターまで含めて、
-
 老化を、止めたいのなら
「今のままでいい」って思ってない?多くの人が、間違っていることに気づかないままなことがあります。それが、「現状
老化を、止めたいのなら
「今のままでいい」って思ってない?多くの人が、間違っていることに気づかないままなことがあります。それが、「現状
-
 何をしても可愛い私のつくりかた
昨夜は美容気功講座「美女STORY第四期」のBeautyキャンプを開催しました。(講義日以外にも、シェアや質問
何をしても可愛い私のつくりかた
昨夜は美容気功講座「美女STORY第四期」のBeautyキャンプを開催しました。(講義日以外にも、シェアや質問